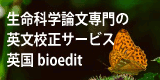2024年度塚原仲晃記念賞受賞者 藤澤 茂義 先生 受賞の言葉
「海馬と嗅内皮質の時空間情報処理機構の研究」
理化学研究所脳神経科学研究センター チームディレクター
藤澤 茂義
藤澤 茂義
このたびは第39回塚原記念賞を賜り、誠に光栄に存じます。私たちの研究を支え、共に歩んでくださった多くの方々に深く感謝申し上げます。私は、記憶や時空間の認識などの脳機能を神経回路レベルで解明することを目指しています。この目標を達成するため、認知行動中のラットなどの動物において、海馬や大脳皮質などの領域から神経生理学的手法を用いて大規模に神経活動を観測し、ニューロンがどのような回路演算を行うことで認知機能に関与しているのかを探究してきました。
人間や動物にとって、自分が経験した出来事を記憶することは、様々な学習過程において重要であるのみならず、社会生活を営む上でも不可欠な脳機能です。ヒトにおいては、過去に生じた出来事を記憶することはエピソード記憶と呼ばれ、脳領域としては海馬がその役割を担っていることが知られられていますが、その詳細な神経回路メカニズムはいまだ明らかになっていません。エピソード記憶を形成するためには、「いつ(時間)」「どこで(空間)」「何をしたか(事物・出来事)」の要素を結びつけて記憶する必要があります。これまで、海馬における空間認識の研究については、げっ歯類を用いた神経生理学研究により大きな進展がみられてきました。とくに海馬には、空間における自己の位置を認識することのできる「場所細胞」というニューロンが存在し、脳内で地図を構成することに役立っています。また、海馬に強い投射をもつ嗅内皮質には、自己が六角形の格子点に当たる場所を通過するときに活動する「格子細胞」というニューロンが存在し、この格子細胞が空間認知のための座標系を構成しています。場所細胞を発見したオキーフ教授と格子細胞を発見したモーザー教授夫妻は、空間認知に関わる脳細胞の発見の成果で2014年のノーベル医学生理学を受賞されるなど、とても注目度の高い研究分野となっています。しかし、海馬において、空間と事物の情報がどのように統合されるか、あるいは時間と事物の情報をどのように統合させて出来事の時系列として記憶できるか、といったエピソード記憶を構成するための神経メカニズムについてはいまだに明らかになっていません。私は、時間・空間・事物の情報が海馬の中でどのように統合されてエピソード記憶の形成へとつながっているかについてのメカニズムを解明することを目的に研究を行ってきました。
この問いに取り組むため、まず出来事の順序を記憶するメカニズムに注目した研究を行いました。私たちは日常の出来事を記憶するとき、それぞれの出来事の内容に加えて、その出来事の起きた順序を覚えることができます。このように経験した出来事の時系列情報を記憶することはエピソード記憶の重要な要素の一つですが、どのような神経回路メカニズムで経験した出来事の内容や順序を記憶しているかは解明されてませんでした。そこで私たちは、ラットを用いた神経系理学実験を行いました。まず、音や匂いなどの異なる感覚情報の統合を必要とする組み合わせ弁別課題をラットに学習させました。そして、その課題を遂行しているときの海馬の神経活動を、超小型高密度電極を用いて詳細に記録したところ、海馬の神経細胞の中に音や匂いなどそれぞれの情報に対して選択的に活動する「イベント細胞」を発見しました。これは、海馬の個々のイベント細胞がそれぞれの出来事の内容を記憶して表現しているということを意味しています。また海馬では、神経細胞の集団の同期活動により生じる強い脳波(シータ波)が観測されることが知られています。そこで、出来事の内容を記憶しているイベント細胞が、シータ波のどのタイミングで活動しているかを調べたところ、海馬の神経細胞は、シータ波の位相によって過去・現在・将来の出来事の順序を圧縮して表現していることが分かりました。この研究によって、海馬の個々のイベント細胞は、その活動の強さによって出来事の内容を表現し、その活動のタイミングによって出来事の順序を表現していることが明らかになりました(Terada et al., 2017)。この発見は、私たちが日常の出来事をどのように記憶し、その時系列をどのように保持しているのかを理解する上で、非常に重要な知見です。
つぎに、他者の空間位置を認識するメカニズムに注目した研究を行いました。これまでに、海馬には場所細胞という自己の空間位置を認識する神経細胞が存在することが知られていました。しかし、自己以外のもの、例えば物体や他者などの空間位置情報がどのように認識されているかは解明されていませんでした。これは、エピソード記憶において場所と事物の情報がどのように統合されるかを明らかにするうえでとても重要な問いとなります。そこで私たちは、社会的環境におかれているラットがどのように他者の空間的位置を認識しているのかのメカニズムを研究しました。この結果、海馬において、自己の位置を認識する標準的な場所細胞に加え、他者の位置を認識する「他者場所細胞」が存在することを発見しました(Danjo et al., 2018)。この結果は、海馬の神経細胞が自己の空間上の位置のみならず、他者の空間上の位置も同時に認識していることを明らかにしたものであり、私たちがどのように自己や他者の空間情報を認識しているかを解明する上で重要な知見となりました。
さらに、このような海馬における時間・空間の認識に、嗅覚内皮質からの入力がどのように関係しているのかを研究しました。とくに、海馬においては空間ナビゲーションにおいて現在から将来の経路を予測するシータ・シーケンスという現象があることが知られていましたが、嗅内皮質から海馬にどのように将来予測の情報が入力されるのかについてのメカニズムは明らかではありませんでした。そこで、私たちは、ラットに目標指向的行動課題を学習させ、この課題を行っているときのラットの嗅内皮質および海馬におけるニューロンの活動を、超小型高密度電極を用いて記録する実験を行いました。その結果、嗅内皮質において、ラットがこれから移動する数十センチメートル先の将来の空間の位置に対して格子表現を持つニューロンを発見し、これを「予測的格子細胞」と名付けました。つまり、予測的格子細胞は、現在の位置ではなく、これから移動する将来の空間の位置に対して格子表現を持つということです。こうした予測的格子細胞は、空間ナビゲーションにおいて、海馬と嗅内皮質のネットワークにおいて将来の移動計画を行う上で重要な役割を担っていると考えられます(Ouchi and Fujisawa, 2024)。
今回の一連の研究を通じて、海馬がエピソード記憶の形成において時間・空間・事物の情報を柔軟に統合する中心的な役割を担っていることが明らかになりました。今後は、これらの知見をさらに深めることで、ヒトを含む多様な生物種における複雑な認知機能や社会的行動の神経基盤を解明し、将来的には認知症や記憶障害などの疾患理解や治療法の開発にも貢献できると期待しています。今回の受賞を励みに、私たちは引き続き、この分野の発展と社会的意義の大きい研究へ邁進してまいります。

藤澤 茂義
理化学研究所脳神経科学研究センター チームディレクター
【略歴】
| 2000: | 京都大学工学部物理工学科卒業 |
| 2005: | 東京大学薬学系研究科博士課程修了、薬学博士 |
| 2005~2012: | ラトガース大学分子行動神経科学センター 研究員 |
| 2012~2012: | ニューヨーク大学医学部神経科学センター 研究員 |
| 2012~2018: | 理化学研究所脳科学総合研究センター チームリーダー |
| 2018~現在: | 理化学研究所脳神経科学研究センター チームリーダー |
| 2019~現在: | 東京大学新領域創成研究科 客員教授 |
| 2025~現在: | 京都大学生命科学研究科 客員教授 |