森茂美先生を偲んで
森茂美先生(旭川医科大学名誉教授・岡崎国立共同研究機構生理学研究所名誉教授・総合研究大学院大学名誉教授)が2025年2月26日に89歳でご逝去されました。 心よりご冥福をお祈り申し上げます。

Sten Grillner 先生(スウェーデン カロリンスカ研究所 教授)からの追悼文も後半に掲載させて戴きます。
旭川医科大学 生理学講座・神経機能分野
東京大学大学院 工学系研究科
高草木薫
東京大学大学院 工学系研究科
高草木薫
森茂美先生は1936年に北海道帯広市で生を受けました。1961年に北海道大学医学部をご卒業され,米国空軍病院(東京都立川市)で一年間の卒後研修を受けられました。医学部の学生時代は北大全学の剣道部主将として剣道の帝大対抗戦においても際立ったご活躍をされた記録が残っております。卒後研修の後に北海道大学の医学部生理学講座(藤森聞一主催)にて大学院を修了されました。大学院修了直前の学会発表において森院生の堪能な英語と切れ味鋭い論理展開は,当時のJournal of NeurophysiologyのChief-EditorであったJohn M Brookhart教授の目に留まり,スカウトされる形で,1966年から1969年までの3年間,米国 オレゴン州立オレゴン健康科学大学のBrookhart教授の元で,当時の姿勢制御の神経学的メカニズムと制御理論を学ばれました(森茂美先生談)。帰国後の1969年には北海道大学医学部の助手を,1973年には同講師をお勤めになりました。そして,翌年の1974年には,若干37歳にて旭川医科大学の生理学第二講座の初代教授として,開学間もない医学部の教育と研究に専念することとなりました。
しかし,森茂美先生は旭川医大赴任直後に,学生の教育を青木藩先生(当時助教授,札幌医科大学名誉教授,故人)らに任せ,単身ソビエト(現ロシア)のモスクワに赴き,中脳歩行誘発野の発見者であるShik MLらと共に,国立アカデミーにおいて「除脳ネコにおける歩行と姿勢に関する研究」に着手しました。ロシアにおける彼の顕著な研究成果は,「姿勢筋緊張を増加あるいは減少させる領域が脳幹に存在すること,そして,筋緊張レベルの違いによって(歩行誘発野の刺激によって誘発される)ネコの歩容が変化する」というものでした。森茂美先生はこの概念をStage-Setter 仮説と命名し,この仮説は,様々な神経疾患における歩行障害の背景には筋緊張調節系の異常が存在するという臨床神経学の基本概念の確立へと繋がって行くことになりました。森茂美先生は1974年から1993年までの19年間,旭川医科大学で,除脳ネコにおける姿勢と歩行の統合機構に関する研究を継続し,脳幹と脊髄における筋緊張調節系(Stage-Setter)を構成する神経回路網とその活動を調節する神経伝達物質の解明などに尽力されました。私見ですが,① ロシアのShik ML らによる中脳歩行誘発野(歩行運動に特化した脳領域)の発見と同定,② スウェーデンのGrillner Sらによる,脊髄の歩行リズム(パターン)生成機構(Central Pattern Generator;CPG)の発見と同定,そして,③ 森茂美先生が発見・同定した姿勢筋緊張制御系の研究業績は,20世紀後半の歩行の神経科学における3大研究であると今でも思っております。研究における森茂美先生の一貫した姿勢は,「当該環境におけるヒトや動物の行動全体を観察すること」でした。神経科学における当時の解析手法の主流が細胞内記録法を駆使した神経回路網の解析であったことを考慮すると,森茂美先生の「全体論的研究手法」は,当時の神経科学分野において異才を放つと共に,小児神経学やリハビリテーション医学分野において重要な概念を提供するものでありました。森茂美先生は,1991年に 旭川においてFirst International Symposium on Posture and Locomotion in Asahikawa と銘打ったPrivate での国際シンポジウムを開催されました。この国際シンポジウムでは,ノーベル賞受賞者を含む運動制御や睡眠調節の研究に携わる世界的研究者を招待しました。3日間に渡る白熱した議論は真に圧巻でした。
森茂美先生は,より国際的な研究展開を目指し,1993年に岡崎国立共同研究機構生理学研究(生体調節研究系・生体システム研究部門)へと研究の主戦場を移しました。 岡崎での最初の業績は,「小脳歩行誘発野」の発見と同定でした。この研究によって,歩行誘発野と呼ばれる脳領域が前脳(視床下部歩行誘発野)と中脳に加えて小脳にも存在することが証明されました。これは歩行(移動)という動物に最も基本的な運動機能が皮質下に分散する各神経領域によって制御されること,そして,各領域の入・出力に依存した歩容が実現することなど,歩行動作の頑健性と多様性を物語る上で重要な研究成果となりました。森茂美先生は,自身の研究者生命を掛けて,二足歩行の神経機構の解明を志すことになりました。ニホンザルに条件付けの歩行動作を学習させ,サルが(四足から)二足歩行を獲得するに至る姿勢と歩容の変化を解析すると共に,二足歩行における大脳皮質運動関連領野(一次運動野・補足運動野・運動前野)の機能特異性の解明を試みました。森茂美先生はその詳細な研究成果の公表を観ることが出来ませんでしたが,「二足歩行の獲得に至る姿勢と歩容の発達」に関する森茂美先生と彼の共同研究者の業績は,脊椎動物の進化やヒトの生後発達,そして,神経疾患における歩行障害のメカニズムを理解する上で極めて重要な知見を提供するものです。
森茂美先生は神経科学学会の理事をお務めになられるなど,本国の神経科学の発展に多大な貢献を果たしました。特に,若い研究者の指導には非常に熱心でした。彼らに大きなチャンスと試練を与えながら,その力を引き出すという彼の指導法は,当時の若手研究者に大きな影響を与えました。また定年後も様々な学問分野の教育に携わりました。定年直後には,米国のArkansas大学の神経科学講座(E Garcia-Rill 教授主催)にて,1年間,同講座の大学院生の研究を指導しました。森茂美先生が見せた帰国後の晴れやかな姿と笑顔は,研究者教育に込める彼の熱意と満足感を示すものだったに違いありません。その後も,特定領域研究「移動知」の審査員として,本国の新学術領域研究の発展に貢献する傍ら,脳科学分野での新たな研究を目指す工学研究者に対しても真摯に神経科学の教育をしておりました。森茂美先生が定年してから二十数年を経た現在でも,国内外の著名な研究者から彼が慕われる理由の一つが,未来を担う研究者へ情熱的な教育指導であるのかも知れません。今や,森茂美先生が提唱されたStege-Setter 仮説はロボット制御などの工学分野における基本的概念の一つとなりました。
森茂美先生は令和7年2月26日,外出先にて発作に襲われ,89歳でこの世を去りました。森茂美先生の御業績と御指導に畏敬の念を込め,ここに謹んで哀悼の意を表し,心からご冥福をお祈りいたします。最後に彼が最も尊敬していた脳研究者の一人であるカロリンスカ研究所のSten Grillner教授からの追悼の文章をご紹介させて戴きます。
しかし,森茂美先生は旭川医大赴任直後に,学生の教育を青木藩先生(当時助教授,札幌医科大学名誉教授,故人)らに任せ,単身ソビエト(現ロシア)のモスクワに赴き,中脳歩行誘発野の発見者であるShik MLらと共に,国立アカデミーにおいて「除脳ネコにおける歩行と姿勢に関する研究」に着手しました。ロシアにおける彼の顕著な研究成果は,「姿勢筋緊張を増加あるいは減少させる領域が脳幹に存在すること,そして,筋緊張レベルの違いによって(歩行誘発野の刺激によって誘発される)ネコの歩容が変化する」というものでした。森茂美先生はこの概念をStage-Setter 仮説と命名し,この仮説は,様々な神経疾患における歩行障害の背景には筋緊張調節系の異常が存在するという臨床神経学の基本概念の確立へと繋がって行くことになりました。森茂美先生は1974年から1993年までの19年間,旭川医科大学で,除脳ネコにおける姿勢と歩行の統合機構に関する研究を継続し,脳幹と脊髄における筋緊張調節系(Stage-Setter)を構成する神経回路網とその活動を調節する神経伝達物質の解明などに尽力されました。私見ですが,① ロシアのShik ML らによる中脳歩行誘発野(歩行運動に特化した脳領域)の発見と同定,② スウェーデンのGrillner Sらによる,脊髄の歩行リズム(パターン)生成機構(Central Pattern Generator;CPG)の発見と同定,そして,③ 森茂美先生が発見・同定した姿勢筋緊張制御系の研究業績は,20世紀後半の歩行の神経科学における3大研究であると今でも思っております。研究における森茂美先生の一貫した姿勢は,「当該環境におけるヒトや動物の行動全体を観察すること」でした。神経科学における当時の解析手法の主流が細胞内記録法を駆使した神経回路網の解析であったことを考慮すると,森茂美先生の「全体論的研究手法」は,当時の神経科学分野において異才を放つと共に,小児神経学やリハビリテーション医学分野において重要な概念を提供するものでありました。森茂美先生は,1991年に 旭川においてFirst International Symposium on Posture and Locomotion in Asahikawa と銘打ったPrivate での国際シンポジウムを開催されました。この国際シンポジウムでは,ノーベル賞受賞者を含む運動制御や睡眠調節の研究に携わる世界的研究者を招待しました。3日間に渡る白熱した議論は真に圧巻でした。
森茂美先生は,より国際的な研究展開を目指し,1993年に岡崎国立共同研究機構生理学研究(生体調節研究系・生体システム研究部門)へと研究の主戦場を移しました。 岡崎での最初の業績は,「小脳歩行誘発野」の発見と同定でした。この研究によって,歩行誘発野と呼ばれる脳領域が前脳(視床下部歩行誘発野)と中脳に加えて小脳にも存在することが証明されました。これは歩行(移動)という動物に最も基本的な運動機能が皮質下に分散する各神経領域によって制御されること,そして,各領域の入・出力に依存した歩容が実現することなど,歩行動作の頑健性と多様性を物語る上で重要な研究成果となりました。森茂美先生は,自身の研究者生命を掛けて,二足歩行の神経機構の解明を志すことになりました。ニホンザルに条件付けの歩行動作を学習させ,サルが(四足から)二足歩行を獲得するに至る姿勢と歩容の変化を解析すると共に,二足歩行における大脳皮質運動関連領野(一次運動野・補足運動野・運動前野)の機能特異性の解明を試みました。森茂美先生はその詳細な研究成果の公表を観ることが出来ませんでしたが,「二足歩行の獲得に至る姿勢と歩容の発達」に関する森茂美先生と彼の共同研究者の業績は,脊椎動物の進化やヒトの生後発達,そして,神経疾患における歩行障害のメカニズムを理解する上で極めて重要な知見を提供するものです。
森茂美先生は神経科学学会の理事をお務めになられるなど,本国の神経科学の発展に多大な貢献を果たしました。特に,若い研究者の指導には非常に熱心でした。彼らに大きなチャンスと試練を与えながら,その力を引き出すという彼の指導法は,当時の若手研究者に大きな影響を与えました。また定年後も様々な学問分野の教育に携わりました。定年直後には,米国のArkansas大学の神経科学講座(E Garcia-Rill 教授主催)にて,1年間,同講座の大学院生の研究を指導しました。森茂美先生が見せた帰国後の晴れやかな姿と笑顔は,研究者教育に込める彼の熱意と満足感を示すものだったに違いありません。その後も,特定領域研究「移動知」の審査員として,本国の新学術領域研究の発展に貢献する傍ら,脳科学分野での新たな研究を目指す工学研究者に対しても真摯に神経科学の教育をしておりました。森茂美先生が定年してから二十数年を経た現在でも,国内外の著名な研究者から彼が慕われる理由の一つが,未来を担う研究者へ情熱的な教育指導であるのかも知れません。今や,森茂美先生が提唱されたStege-Setter 仮説はロボット制御などの工学分野における基本的概念の一つとなりました。
森茂美先生は令和7年2月26日,外出先にて発作に襲われ,89歳でこの世を去りました。森茂美先生の御業績と御指導に畏敬の念を込め,ここに謹んで哀悼の意を表し,心からご冥福をお祈りいたします。最後に彼が最も尊敬していた脳研究者の一人であるカロリンスカ研究所のSten Grillner教授からの追悼の文章をご紹介させて戴きます。
Shigemi Mori – in memoriam
Sten Grillner
Karolinska institutet,
Stockholm
Karolinska institutet,
Stockholm
I am very sad to have lost a dear colleague, Shigemi Mori, whom I have known over more than half a century. On a visit to John Brookhart´s laboratory in 1969, I came in contact with the elegant studies of postural control in dogs with different perturbations, performed by Shigemi Mori, who had just returned to Japan after a very creative postdoc! My next encounter some years later was through professor Toshinori Hongo, who wrote to me asking advice about Mori´s plans to spend some time in Moscow to learn the decerebrate walking experimental model that had been pioneered by Gregori Orlovsky and Mark Shik in Moscow. This unique preparation allowed studying the neural bases of a complex integrated behaviour, locomotion, and also posture in a reduced preparation. I had previously been working in Moscow the spring of 1971 and now it was Shigemi Mori´ turn. He spent a very productive time in Moscow elucidating new brainstem-areas that could control locomotion, before returning to Asahikawa, where he rapidly created a very impressive research group. The main focus was the cellular bases of postural control, in which field he became the leader. The brainstem commands for increasing or decreasing the postural tone were in focus and how these commands were translated into action by the spinal cord circuits through very demanding and painstaking experiments.
In 1984 Drs Mori and Hongo invited me to visit Japan, and I then spent a week in Mori´s laboratory and enjoyed taking part in experiments, a fabulous hospitality and experiencing the great enthusiasm of his young collaborators. Later, one of them Yoshihiro Ohta joined me, as a very talented postdoc. I revisited Asahikawa in 1991 when he arranged a very successful symposium. Some years later he decided to move to the well-known National Research institute for Physiology in Okazaki, where he continued his analyses of posture and locomotion, and their relation. An appropriate muscle tone in postural muscles is a precondition for locomotion. His last major research program was to train quadrupedal macaques to walk bipedally and explore what adaptations occurred in cortical motor areas with the intention to understand the different control mechanism that had evolved to account for the human locomotor control.
I had the privilege to meet and interact with Shigemi Mori not only in Asahikawa, Okazaki and Stockholm but in many places around the world. It was always a great pleasure to meet him with his forceful and enthusiastic personality discussing science as well as any other problem and to see how he cared for his young collaborators.
We will all miss him.
森茂美先生 略歴
昭和11(1936)年9月23日生まれ(北海道帯広市)
昭和36(1961)年3月,北海道大学医学部卒業
昭和36(1961)年4月,米国空軍病院(東京都立川市)で卒後研修
昭和37(1962)年4月,北海道大学大学院医学研究科入学(医学部生理学講座 藤森聞一教授)
昭和41(1966)年3月,同修了(医学博士)
昭和41(1966)年3月,米国オレゴン州オレゴン健康科学大学留学(John M Brookhart教授,昭和44年5月まで)
昭和44(1969)年6月,北海道大学医学部助手
昭和48(1973)年9月,北海道大学医学部講師
昭和49(1974)年4月,旭川医科大学教授(第二生理学講座)
平成5(1993)年4月,岡崎国立共同研究機構生理学研究所教授(生体調節研究系・生体システム研究部門)
平成5(1993)年10月,総合研究大学院大学教授
平成14(2002)年3月,岡崎国立共同研究機構生理学研究所名誉教授,総合研究大学院大学名誉教授
昭和36(1961)年3月,北海道大学医学部卒業
昭和36(1961)年4月,米国空軍病院(東京都立川市)で卒後研修
昭和37(1962)年4月,北海道大学大学院医学研究科入学(医学部生理学講座 藤森聞一教授)
昭和41(1966)年3月,同修了(医学博士)
昭和41(1966)年3月,米国オレゴン州オレゴン健康科学大学留学(John M Brookhart教授,昭和44年5月まで)
昭和44(1969)年6月,北海道大学医学部助手
昭和48(1973)年9月,北海道大学医学部講師
昭和49(1974)年4月,旭川医科大学教授(第二生理学講座)
平成5(1993)年4月,岡崎国立共同研究機構生理学研究所教授(生体調節研究系・生体システム研究部門)
平成5(1993)年10月,総合研究大学院大学教授
平成14(2002)年3月,岡崎国立共同研究機構生理学研究所名誉教授,総合研究大学院大学名誉教授
令和7年2月26日没,享年89歳
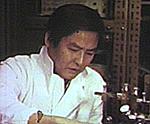
実験中の森茂美先生
(40歳前半)
(40歳前半)





